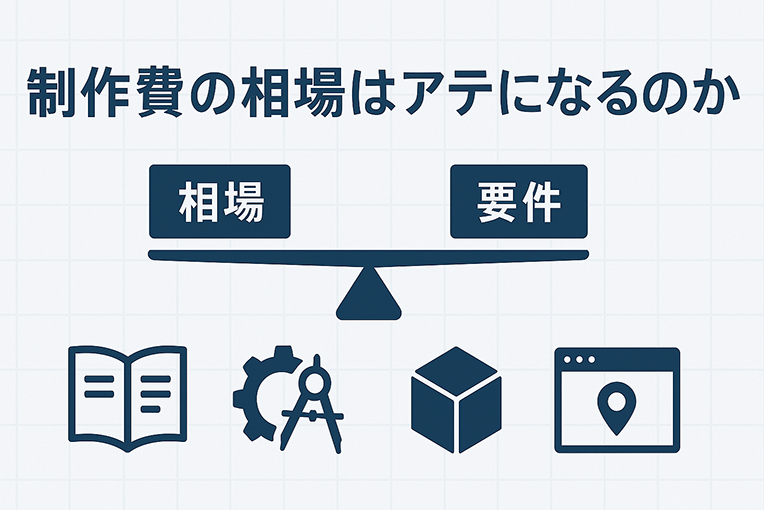クリエイター目線と発注者目線からの実感値
弊社の主たる業務内容として製品マニュアル、テクニカルイラスト、CG、地図、そしてWeb開発——どれも「相場感」を尋ねられる領域です。検索すれば価格表も見つかります。では、その相場は“アテ”になるのか。結論から言うと、参考にはなるが、判断の拠り所にし過ぎると危うい。理由はシンプルで、成果物の「見た目」が似ていても、到達するまでの難易度と工数がまるで違うことが珍しくないからです。
以下では、クリエイター(作り手)と発注者(依頼側)の双方の視点で、相場がズレる要因を具体的に分解し、最後にAIやソフトウェア進化の影響まで含めて整理します。
相場が外れそうなポイント
- 要件の具体度:
- 発注者目線:社内合意が未確定のまま見積を急ぐと、後工程で要件が膨らみがち。
- クリエイター目線:曖昧さはリスク。バッファを載せる=相場より高く見える。
- 元データの品質:図面の欠落、古い仕様、写真の解像度不足は手戻りの温床。
- レビュー体制(承認フロー):確認者が多いほどフィードバックの往復が増える。日程=コスト。
- 運用前提:更新頻度や多言語展開、アクセシビリティ対応など、納品後の前提が積算を左右。
- 異常ケース対応:マニュアルやWebは例外処理ほど工数が嵩む。目に見えないが重い。
- リスクと責任範囲:保証・瑕疵・保守SLAの強さに比例して見積は厚くなる。
- スケジュールの硬さ:納期が硬直している案件は人員増や夜間対応が前提になり、相場から乖離しやすい。
どこで相場が揺れるのか
1)製品マニュアル作成
- ズレ要因:情報源の整理(仕様・図面・試作機アクセス)、版管理、法規適合(PL法/安全表示)、多言語展開。
- ポイント:同じページ数でも、情報設計(章立て・記号体系・警告の階層)が成熟しているかで工数が倍違う。試作機に触れられるか否かも決定的。
- 発注ヒント:最低限の「正本データ」「リスク評価」「想定ユーザー像」を初回提示できると、相場に近い見積が出やすい。
2)テクニカルイラスト
- ズレ要因:参照図面の精度、爆発図/分解図の複雑さ、寸法公差の扱い、陰線処理ルール、最終媒体(印刷/オンスクリーン)。
- ポイント:部品点数×断面表現×投影法の組合せで指数関数的に難度が上がる。見た目はシンプルでも、正確さの裏取りに時間が出る。線を少なくすれば安くなる?なりません!!
- 発注ヒント:図面の信頼度(版数・日付)と変更可能範囲(正確性か納期か)を明示。
3)CG作成
- ズレ要因:モデリングの起点(CAD/ゼロから)、マテリアルの現物合わせ、アニメーション尺、レンダリング品質、演出意図。
- ポイント:最も“見た目”に引っ張られやすい分野。1カットでもラフ→ルックデブ→本番の段階ごとに手戻りコストが大きい。
- 発注ヒント:使途(展示/営業/教育/配信)と再利用計画(静止画切り出し・尺違い)をセットで伝えると設計が合理化できる。
4)地図作成
- ズレ要因:ベースデータのライセンス、測地系・投影法、更新頻度、注記言語、成果物がソースデータか印刷かWebか(タイル/ベクター)。
- ポイント:正確性・可読性・美観の三すくみ。特に法定地図や案内図は責任が重く、検証工数がかさむ。
- 発注ヒント:縮尺・用途・更新サイクルを最初に固定。権利関係(出典・クレジット)も早めに整理。
5)Web開発
- ズレ要因:要件定義の幅(CMS/会員/決済/検索/多言語/デザイン)、表示速度・アクセシビリティ、セキュリティ要件、運用体制(誰が更新するのか)。
- ポイント:初期制作費だけでなく保守・運用コストが実態。要件を削って初期費を下げても、運用で積み上がるなら本末転倒。
- 発注ヒント:KPI(問い合わせ数・CVR・表示速度など)と運用担当の実情(社内or外部)を共有するほど、適正価格に近づく。
そこで「見えない難易度」をどう扱うか
- データ整備:欠落情報の補完、命名規則の統一、版管理の導入は、制作以前の土台だが大きなコストドライバー。
- レビュー設計:誰が何を持って「OK」を出すのか。決定者が後から現れると、一回の修正が丸ごとやり直しになる。←界隈でアルアル
- 検証と責任:法務・安全・表記統一など、成果物の品質保証はコストに反映すべき項目。相場表に記載されにくい。
AIとソフトウェア進化は相場を下げるのか?
一部は下がるが、全体は“再配分”が現実的でしょうか。よく目にするのが、
- 効くところ:
- テキストの下書き、表現ゆらぎの統一、用語抽出、画像のノイズ除去、簡易な背景生成、既存マップの注記支援など。
- 単純繰り返しや“型化できる”タスクはスピードと安定感が向上。
- 効きにくいところ:
- 実機検証、責任が重い記述(安全/法令)、独自性の強いアートディレクション、クリティカルなUI設計や情報設計。
- 結論:単価が下がるのではなく、要件定義・設計・検証に重心が移り、そこで価値が可視化される。AIを活かすほど、前工程の精度と後工程の検証が重要になる。
相場に近づけるためには?
この5点だけで精度が跳ね上がるのでは。
- 目的:何を達成したいか(例:不具合問い合わせ30%削減)。
- 対象と使用環境:誰が、どこで、どの媒体・縮尺・端末で使うか。
- 範囲(やらないことも含む):今回の対象外を明記。
- 元データのリストと信頼度:最新図面・仕様・写真・テキストの所在と版数。
- 意思決定フロー:最終決裁者、レビュー回数、締切の硬さ。
迷ったら「サンプル1点を先に作る」とか。小さく試して学び、残りを精算するのが最短で安いのでは無いかと思うのだが、サンプルも何でもかんでも”ただ”では厳しい。。。
結局のところ。。。
相場は“方向”であって“答え”ではないってことですかね。ゼロから考える際の座標にはなります。しかし最終価格は、要件の具体度・データ品質・承認フロー・責任範囲・納期の硬さで大きく変動します。ましてAIとソフトウェア進化は単価を下げるのではなく、価値の集中点を前工程と検証に移し、失敗を減らすことに役立つように思います。
さて、それぞれ抱える案件で「相場」を信じるべきは、どの部分で、どの部分は検証すべきでしょうか?
テクニカルイラスト | CG | WEB開発
マニュアル制作 | 地図編集
株式会社テクノアート
大阪府 池田市